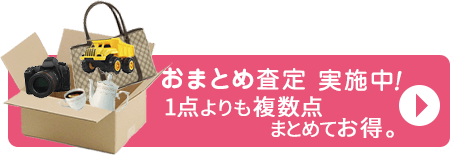マイセン コーヒーカップ

18世紀初頭のヨーロッパでは、まだ白磁の秘密を発見しておらず、コーヒーカップは輸入していました。世界の食器の原点といわれている中国の景徳鎮や日本の伊万里焼の湯のみをカップ代わりに使っていたのです。
湯のみですので取っ手部分が無く、マイセンもそれにならって写真のようなコーヒーカップを作っていました。
時代が進むにつれて取っ手がつけられたり、カップの大きさが多様化したりと様々な工夫がみられるようになりました。
マイセンの湯のみ型コーヒーカップ

18世紀初頭、マイセン窯がハンドルのあるコーヒーカップを作るまでは湯呑みが使われていました。
コーヒーがヨーロッパに伝わった当初、マイセンは誕生しておらず、ヨーロッパでは磁器を作る技術がありませんでした。
そのため中国や日本から湯呑を買い付け、コーヒーカップの代替にしていました。このハンドルなしのマイセンコーヒーカップは東洋文化の名残だといわれています。
マイセンの定番コーヒーカップ

こちらはマイセンで定番のピンクローズのコーヒーカップです。
先に紅茶文化がヨーロッパに普及していたこともあり、コーヒーカップにも取っ手がつけられるようになります。
紅茶は熱いお湯で煎れるため、持ち手への配慮が必要だったことと、カップに描かれた図柄が飲む人側に向くようにというのが理由です。
これは紅茶文化を広めたイギリス様式(礼儀作法を重んじる)を見習ってのことだといわれています。
□■カップの形状□■
カップの形状にも注目です。ティーカップよりも背高で小さい作りになっているのがわかりますでしょうか。
この形状になった背景として、コーヒー発祥の地、トルコでの当時の文化が根底にありました。9世紀頃のトルコではコーヒー豆は貴重だったため、薬として飲まれていました。飲むときには小さなカップを使用し、臼で挽いた豆粉を手鍋に入れてぐつぐつと煮出してからさまし、上澄みだけ啜っていたそうです。
コーヒーカップが背高なのは上澄みを飲むためであり、高温の飲み物ではなかったことから、口を広くして空気に触れさせる必要がなく、小さい作りになったのです。
□■ソーサーの作り□■
ソーサーもティーソーサーに比べて深くて広いのがお分かりいただけますでしょうか。こちらは上澄みをこぼさないため。。。ではなくて、、こちらはヨーロッパの食文化からきています。
ヨーロッパでは中世前まで手掴みで食事をしていたようで、手で取って食べやすいように平たい食器、ディッシュというものが好まれていました。
そこにコーヒー文化がやってきたとき、ヨーロッパの紳士淑女はディッシュにコーヒーを注いで飲んでいました。とはいっても平皿なので当然こぼれます。
そこで受け皿の役目をするソーサーが添えられることになります。
コーヒーは単体で飲まれることよりも、食事と一緒という文化だったため、広くて深いソーサーがあてがわれることになったのです。
カップとソーサーに思いをはせて

マイセンの豊富な種類のカップとソーサー、形状もさることながらその絵柄にも注目する人は多いはずです。
外国から来た絵柄や模様、人物像であったり、植物であったり。
マイセンもたくさんのコーヒーカップを出していますが、今回注目していただきたいのは物語シリーズ。コーヒーカップとソーサーで一つの物語になっているのはマイセンの魅力です。
写真のシリーズはマイセンのアラビアンナイト。ハインツ・ヴェルナー氏デザインです。ップ、プレートともに12柄あります。
「アラジンと魔法のランプ」を題材にカップにはアラジンと姫の二人が空中に浮遊している図案が色鮮やかに描かれています。ソーサーにはその二人をやさしく受け止めるかのように魔法のじゅうたんが繊細に絵が画れています。
貴族や知識人のお茶会やサロンではカップに描かれた絵を話題にし、おのおのの知識を披露していたそうです。